マネー現代に掲載されていた記事です。インデックス投資の記事かと思いきや、予想外の中身でした。
高配当投資
外部リンク:マネー現代 小難しい理論、知識はいらない…「投資の素人」が最少の努力で最大のパフォーマンスを上げる「株式投資法」の中身
さすがに、元著名経済誌の編集長をされていただけあって文章は、プロです。一見説得力に溢れています。最大のパフォーマンスを上げる「株式投資法」とは、業界トップ企業の高配当株式に分散するということのようです。理由付けが匠で、株式投資をこれから始めようとするときこの文書を読むと目から鱗になるかもしれません。ブログ主も心底お上手だなと惚れ惚れしました。
ところがです。よく読んでみると疑問点がそこかしこに隠れています。
どの業界でも、トップ企業には資本力や経営ノウハウ、人材がそろっている。下位の企業に比べ生き残れる可能性が高い。
たとえば繊維やカメラの銀塩フィルムのようにグローバル化や技術革新で業界全体が斜陽化しても、東レや富士フイルムのような業界トップ企業であればあざやかな業態転換によって企業としての生き残りをはかることができた。
出典:マネー現代 小難しい理論、知識はいらない…「投資の素人」が最少の努力で最大のパフォーマンスを上げる「株式投資法」の中身
なるほどと思わされる一方、繊維ではカネボウ、カメラは、コダックなど生き残れなかったトップ企業には触れられていません。JALや東電、ダイエーなどを思い浮かべても、「生き残れる可能性が高い」と言い切れるかは疑問です。
特に技術革新が起こり得る場面では、レガシーコストが足かせとなり、旧来の巨大企業が新興企業にひっくりかえされることが繰り返されています。
「偉大な企業はすべてを正しく行うが故に失敗する」・・・反対の事象も知っておくべきです。
『会社四季報』にはROE(株主資本利益率)、ROA(総資産利益率)、CF(キャッシュフロー)、PBR(株価純資産倍率)、PER(株価収益率)などの指標がたくさん記載されている。しかし株式投資の素人にはその意味や活用法がよくわからない。計算方法も面倒そうだ。
だが心配しなくてよい。こうした細かな指標はプロ向けの情報である。個人投資家は知っておいて損はないが、知っているからといって投資のパフォーマンスが上がるとはかぎらない。
<中略>
プロのディーラーやファンドマネジャーが短期間で多くの銘柄に投資しなければならない場合には必須の道具となるが、少数の銘柄しか投資できない私たち個人投資家には、ほとんど必要ないツールといっても言い過ぎではない。
出典:マネー現代 小難しい理論、知識はいらない…「投資の素人」が最少の努力で最大のパフォーマンスを上げる「株式投資法」の中身
難しいことは知らなくてもいいですと素人を安心させる書き方は上手いのですが、さすがに個別株投資を勧めるうえで、書かれている基本的な指標を知らなくてもいいというのは、行き過ぎではないでしょうか。
さらに、さらっと「少数の銘柄しか投資できない」と書かれています。前ページでは、「業界のトップ企業のあいだで分散投資を行なえば、株価の変動や減配・無配のリスクを大きく減らすことができる。」との結論でしたので、これでは、分散投資できませんが・・・・・。
私たちが知っておくべきは、株式投資したおカネが年間の配当金でどのくらいの利益を生み出すか(=配当利回り)という投資尺度だ。
この「利回り」というものは金融商品に共通の尺度だ。配当利回りが債券利回りや預金金利に比べていかに有利か、不利かを知っておけばよい。
出典:マネー現代 小難しい理論、知識はいらない…「投資の素人」が最少の努力で最大のパフォーマンスを上げる「株式投資法」の中身
配当金は、会社が得た「利益」の内、一部が株主に還元されたものに過ぎません。株式投資の投資尺度を配当利回りに置くのは明らかなミスリードです。
配当利回りが高い=正義ではありません。配当利回りが高いのは、否定的な側面も伴っていることが多いです。市場が飽和して事業拡大の余地がないため、本業での事業投資をおこなえない場合や、収益力が低下して将来が悲観的に見られているため、株価が下がり一時的に高配当になっている場合もあります。本業が好調なら、配当よりも再投資にまわして、将来の成長を図ったほうが、株主にとって遥かに有益です。
指数でみてみると、配当利回りが低いナスダック指数とそれよりは高いS&P500やダウ指数でどちらがリターンが高かったかみれば一目瞭然です。

経済誌の編集長の立場にあった方ゆえ、知らないはずがありません。
収益性や財務の健全性で重大な疑義があれば、証券のアナリストや経済記者が素早く嗅ぎつけて、すでに警鐘を鳴らしているはずだ。トップ企業ほど「炭鉱のカナリア」が多くいる。
出典:マネー現代 小難しい理論、知識はいらない…「投資の素人」が最少の努力で最大のパフォーマンスを上げる「株式投資法」の中身
ここも、一瞬なるほどと思わされます。しかし、一般人のもとに情報が到達する頃には既に株価にしっかり反映されてしまっています。個別企業の危機を事前に察知して個人が売り抜けることなど不可能です。
また逆に聞きと判断して損切りしたら、そこが絶好の買い場だったということもあるでしょう。株が値付けされているということは、プロ同士がプロの判断で特定の値段で売ったり買ったりしているわけです。個人でプロを出し抜く判断を行い続けることは不可能ではないでしょうか。PERなどの株式の指標は知らなくていいと言われていたのですが・・・・・・・・。
意図は?
高配当利回りの業界トップ企業へ長期投資することは、個人の投資家が、最少の努力で、最大のパフォーマンスをあげる最良の投資手法なのだ。
出典:マネー現代 小難しい理論、知識はいらない…「投資の素人」が最少の努力で最大のパフォーマンスを上げる「株式投資法」の中身
インデックス投信を上回り続けるアクティブ投信は、ごく僅かで、事前にそれを選択することは困難であるのが定説です。にもかかわらず、高配当投資が、素人が簡単に「最大のパフォーマンスをあげる最良の投資手法」と言い切れるかは疑問です。
問題にされ続けている毎月分配型投信と同じ匂いがします。高配当であればあるほど収益が得られているという錯覚に陥ってられるのでしょうか。インデックス投資など他の投資手法と比較してメリット・デメリットをきちんと提示してほしいところです。著者ほどの立場にいらっしゃった方が知らないはずありませんので、ミスリードする意図が本当にわかりません。
最後までお読みいただきありがとうございました。
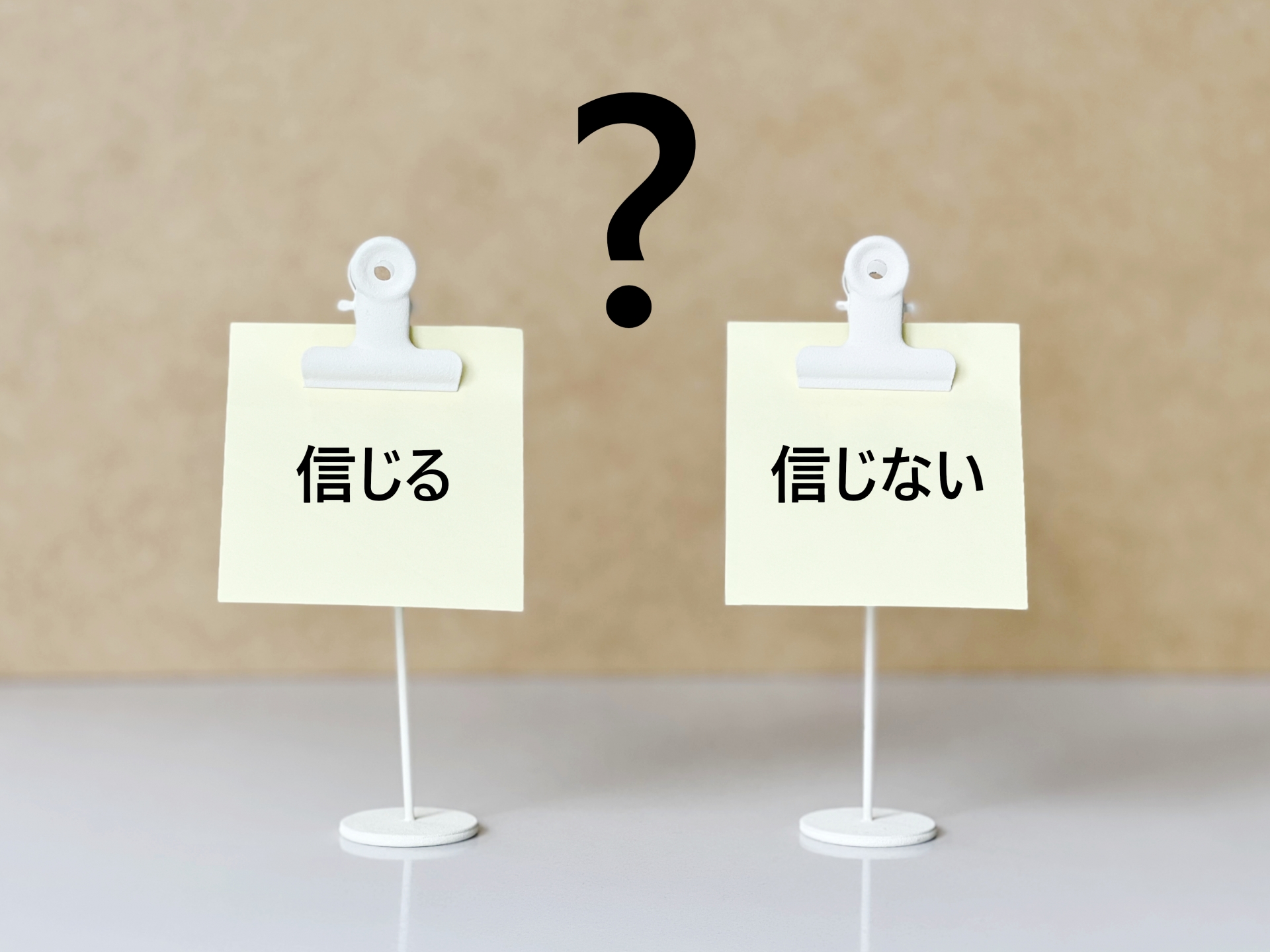



コメント